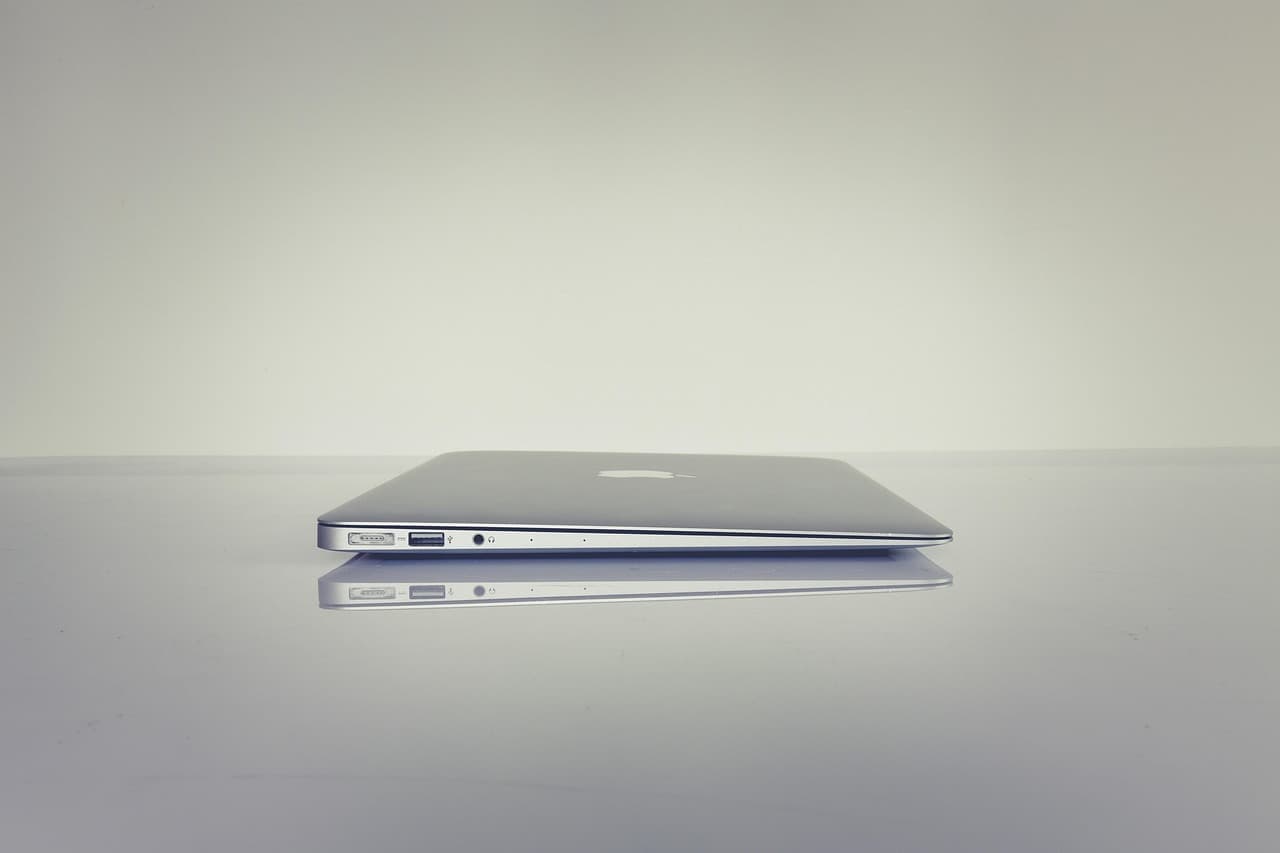AI初心者
SNSのネット広告などでAI漫画がアツいってよく広告などでみるけど、実際はどうなの?
近年、生成AIの進化は「漫画制作」というクリエイティブ領域にまで広がっています。従来は専門的な画力や時間が求められていた漫画制作ですが、いまやAIツールを活用することで、初心者でも短期間で作品を仕上げられる時代になりました。しかも、その作品を電子書籍やSNSを通じて収益化する事例が次々と生まれています。
本記事では、「AI漫画でどうやって稼ぐのか?」に焦点を当て、最新の制作手法や成功事例を交えながら、収益化のロードマップを徹底解説していきます。
そもそも「AI漫画」とは?

生成AIでできること:イラスト生成・ネーム構成・吹き出し配置まで
AI漫画とは、Stable DiffusionやMidjourneyといった画像生成AIや、ChatGPTなどのテキスト生成AIを組み合わせて制作する新しい形の漫画です。
- イラスト生成:キャラクターの立ち絵、背景、表情差分などをAIが出力
→Stable DiffusionやMidjourneyなどの画像生成AI - ネーム構成:ストーリー展開やコマ割り案をAIに提案させる
→ChatGPTなどのテキスト生成AI - 吹き出し配置:自動でセリフを挿入したり、バランスを整えるツールも登場
従来のように「すべて手作業で描く」のではなく、AIをアシスタントとして使うことで、短時間で完成度の高い漫画を量産できるのが大きな特徴です。
従来との違いとクリエイターへのインパクト
従来の漫画制作は「画力 × 膨大な時間」が必須条件でした。そのため、多くの人が「描きたい物語はあるけど絵が描けない」という理由で断念していました。
AI漫画の登場によって:
- 絵が描けなくても漫画が作れる
- プロットやストーリーを重視する人が表現できる
- 小規模チームや個人でも連載が可能
こうした変化は、漫画制作のハードルを劇的に下げ、「物語を持つ人すべてがクリエイターになれる」という新しい潮流を生んでいます。
AI漫画の市場規模と拡大傾向(データ引用)
AIクリエイティブ市場は、2023年から急速に拡大しており、特に漫画・イラスト領域は注目度が高い分野です。
- 株式会社矢野経済研究所の調査によれば、生成AI市場は2025年に1兆円規模に成長すると予測されています。
- 海外でもWebtoon市場が急伸しており、AIを活用した新規参入者が増加。日本国内でも**「AI漫画をKindleで出版して収益化」**する個人クリエイターが増えています。
つまり、AI漫画は一過性のブームではなく、新たな産業の柱になりつつあるのです。
AI漫画で収益化するための5つのルート
AI漫画はただ描いて公開するだけではなく、適切なプラットフォームや仕組みを活用することで収益化が可能です。ここでは、実際に多くのクリエイターが実践している5つのルートを紹介します。
1. Kindle出版での電子書籍販売(Rootport氏の事例あり)
AI漫画で最も分かりやすい収益化方法がKindle出版です。
Amazon Kindleは個人でも手軽に電子書籍を出版できる仕組みが整っており、印税率は最大70%。
実例として有名なのが、Rootport氏による全編AI生成漫画『サイバーパンク桃太郎』です。
- Midjourneyでイラスト生成
- ChatGPTで脚本・セリフを作成
- わずか6週間で108ページを完成させ出版
結果、SNSを通じて大きな話題となり、電子書籍ランキングでも上位に入りました。
AI漫画の収益化を「王道」として目指すなら、Kindle出版は最初に検討すべきルートです。
2. noteやBOOTHなどでの有料販売・定期購読モデル
Kindle以外にも、noteやBOOTHを活用することで、
- 単話販売(1話ごとに数百円)
- 定期購読(月額制の読み放題)
といった仕組みで収益化が可能です。
特にnoteは「記事+漫画」の組み合わせができるため、漫画だけでなく制作裏話や解説記事を添えて有料化する事例が増えています。
また、BOOTHではPDF販売が中心ですが、グッズ化(ポスターや同人誌)との組み合わせで収益を伸ばしているクリエイターもいます。
3. SNSやpixivでのファン獲得 → 支援・投げ銭(PixivFANBOX、Skeb)
AI漫画の収益化では、ファンコミュニティを作ることも重要です。
- PixivFANBOX:月額課金で支援してくれるファンを集め、限定漫画や設定資料を公開
- Skeb:リクエストベースでキャラ漫画を制作して報酬を得る
特にAI漫画は「大量生産が得意」なので、リクエストに応じて短編や1コマ漫画を提供するのに向いています。
SNSで無料公開 → ファンが増える → 支援につながる、という流れを意識すると安定した収益を作りやすいです。
4. クラウドファンディング(Campfire、CAMPなど)
「本格的に単行本化したい」「大型企画をやりたい」という場合は、クラウドファンディングが有効です。
- CampfireやCAMPでは漫画制作プロジェクトの募集が増えており、AI漫画も注目を集めています。
- 「AI漫画をフルカラーで単行本化したい」など、明確な目標とサンプルを提示することで支援を得やすくなります。
- 支援者へのリターンとして、限定原稿データやサイン入りデータを提供する事例もあります。
AI漫画は「話題性」が強いため、クラファンとの相性は抜群です。
5. 企業・メディアからの制作依頼(ポートフォリオ活用)
最後に、長期的に安定収益を狙うなら企業案件の獲得です。
AI漫画をポートフォリオとして公開しておくと、
- ゲーム会社のプロモーション漫画
- アプリ紹介の4コマ漫画
- 商品広告用の漫画LP
などの案件依頼につながる可能性があります。
実際、AIを活用してスピーディに納品できる点は企業にとって魅力的であり、「AIを使える漫画家」は今後の需要が高まると予想されます。
収益化成功事例3選【2025年最新版】
AI漫画は「収益化できるのか?」という疑問に対して、すでに明確な答えを出しているクリエイターたちがいます。ここでは、2025年時点で注目すべき成功事例を3つ紹介します。
① Rootport氏:MidjourneyとChatGPTによる108P漫画 → 書籍化成功
AI漫画ブームの火付け役とも言えるのがRootport氏です。
彼は2023年、Midjourneyで絵を生成し、ChatGPTで脚本やセリフを作成する手法を取り入れ、わずか6週間で108ページの長編漫画『サイバーパンク桃太郎』を完成させました。
この作品はAmazon Kindleで出版されるや否やSNSで拡散され、**「世界初の全編AI漫画」**としてニュースメディアにも取り上げられました。さらに電子書籍だけでなく紙書籍化まで実現し、AI漫画の可能性を世に広めた代表的な成功例となっています。
ポイント
- 長編でもAIを組み合わせれば短期間で制作可能
- 話題性を活かしたSNS拡散が収益化に直結
② まにまに氏:生成AIを用いた連載投稿→SNSでバズり→有料公開
次に紹介するのは、SNSでバズを活用した収益化の好例、まにまに氏。
彼は生成AIを用いた漫画をTwitter(現X)やnoteに連載形式で投稿し、キャラクターのユニークさとストーリー性で大きな注目を集めました。
SNSで無料公開したエピソードがバズると、続きや完全版をnoteで有料公開。ファン心理をうまく利用し、無料→有料の自然な導線を作り出しました。
ポイント
- SNSで認知を広げ、ファンを獲得
- 有料公開への導線をしっかり設計することで収益化
③ 野火城:AIイラスト×創作プロットで月5万円の継続収益化
最後に紹介するのは野火城氏のケース。
彼は自作のオリジナルプロット(物語構成)とAIイラスト生成を組み合わせ、定期的に短編漫画を制作。これをPixivFANBOXやBOOTHで展開し、月額支援+有料販売の二本立てで収益を得ています。
特に特徴的なのは「AI任せにせず、自分の物語性を前面に押し出す」スタイル。読者はAI生成部分よりも独自の世界観やキャラクターに魅力を感じ、安定的に支援を続けています。
その結果、毎月約5万円の安定収益を確立しており、AI漫画を副業やセミプロ活動として成立させています。
ポイント
- 独自プロットとAIを組み合わせることで差別化
- 支援モデルを活用し、継続収益を確保
成功の共通点
これら3つの事例に共通するのは、「AIツールを使うだけでなく、話題性・物語性・収益導線を工夫している」ことです。
単にAI漫画を作るだけでは稼げませんが、正しい戦略を取れば確実に収益につなげられることが分かります。
AI漫画制作に使えるツールとその活用法
AI漫画を効率的に制作するためには、用途に応じたツール選びが重要です。ここでは、実際に多くのクリエイターが利用している代表的なツールをカテゴリ別に紹介します。
イラスト生成系(Stable Diffusion、Midjourney、Leonardo.Ai)
- Stable Diffusion
無料かつオープンソースで、自由度が非常に高いのが魅力。LoRAやControlNetなど拡張機能を組み合わせれば、キャラクターの一貫性やコマごとの演出も自在に操作可能。ローカル環境での利用もでき、商用利用にも向きます。 - Midjourney
SNSでのバズ作品を多数生み出した有名AI。高品質なビジュアル表現に強く、特に独特な絵柄や雰囲気を作りたい人に最適。ただし細かな一貫性のコントロールは難しく、「短編・1話完結型漫画」に向いています。 - Leonardo.Ai
漫画風やアニメ調のスタイルに特化しているプラットフォーム。UIが初心者向けで、即座に「漫画らしい」仕上がりが得られるのが特徴です。商業案件でも使われ始めています。 - Nano Banana(ナノバナナ)
- 正式名称は Google の Gemini 2.5 Flash Image モデル。主に画像編集・キャラクタ一貫性補正能力が強みで、既存画像の表情変化や服装変更などを自然に行える点で評価されています。
- → AI漫画において、「このコマだけ表情変えたい」「服装差分を出したい」といった微調整用途で重宝します。
- Seedream
- テキスト → 画像生成能力が強く、様々なスタイルを扱える汎用性を持っています。Seedream 3.0 など最新モデルでは高画質・高速処理が強化されており、漫画的ビジュアルを短時間で得られる可能性があります。
- → 背景、モンスター、風景など「一発で決めたい」パーツに使うと効率的です。
ネーム・ストーリー支援系(ChatGPT、NovelAI)
- ChatGPT
ストーリーの骨組みや会話文の生成に圧倒的な強み。- 「4コマ漫画のプロットを考えて」
- 「バトル漫画の第一話ネームを提案して」
など、要望に応じたアウトラインを瞬時に生成してくれます。
- NovelAI
テキスト生成に特化した海外サービス。キャラクターの会話や設定を細かく展開できるため、物語重視型の漫画に適しています。英語がベースですが、日本語ユーザーも増加中。
コマ割り&編集系(ComicsMaker.ai、Comic Copilot、Canva)
- ComicsMaker.ai
画像をアップロードするだけで、コマ割りや吹き出しを自動生成。長編漫画の効率的な編集に役立ちます。 - Comic Copilot
AIが「ネームから完成原稿まで」を半自動で仕上げる実験的なサービス。まだ新しいツールですが、ネーム作成の補助として便利。 - Canva
本来はデザインツールですが、吹き出しやレイアウト編集が簡単にできるため、AIで生成したイラストを漫画形式にまとめる用途で人気。
一貫性を担保するLoRA活用テクニック(上級編)
AI漫画制作で最大の課題が「キャラクターの一貫性」です。ここで役立つのがLoRA(Low-Rank Adaptation)。
- 特定のキャラLoRAを学習させることで、髪型・服装・顔立ちを統一したイラストを安定的に生成可能。
- 長編作品やシリーズ化を目指すなら、LoRA導入はほぼ必須です。
- 学習済みLoRAを探すだけでなく、自作LoRAを訓練してキャラクターを固定化すると、オリジナル性が高まります。
実践ポイント
- 同じポーズや角度の差分を大量に作ると精度が上がる
- ControlNetと組み合わせて「同じキャラを違うシーンに登場させる」技術が有効
AI漫画を「売れる作品」に仕上げるためのポイント
AIで漫画を作ることは簡単になりました。しかし「売れる作品」にするには、単に生成するだけでは不十分です。ここでは収益化に直結する4つの重要ポイントを解説します。
ジャンル選定:ファンタジー、SF、恋愛が今アツい
売れるジャンルにはトレンドがあります。
- ファンタジー:世界観をAIで一気に描けるため、読者を引き込む力が強い。
- SF:AIならではの近未来的ビジュアル表現が映えやすい。
- 恋愛:ストーリーの共感性が高く、SNSでシェアされやすい。
特に「異世界ファンタジー × 恋愛」の組み合わせはKindleやWebtoon市場でも人気が高く、AI漫画との親和性が抜群です。
プロンプト設計術:キャラの個性を出すテクニック

AI漫画でありがちな失敗が「キャラの顔が毎回違う」こと。これを避けるために:
- プロンプトにキャラクターの明確な特徴(髪色・服装・表情)を必ず指定
→モデルやアプリによってプロンプトの指定方法が異なったり、得意不得意があるので、試しながら理想に近づけるようにすると良い。 - LoRAやキャラ専用モデルを活用して一貫性を担保
→アプリによってはLoRAを作成できるものもあるので、20枚程度の表情や、動き、体の向きを変えるなどした画像を用意して、LoRAを作成すると、一貫した画像が生成されやすくなる。
例えば、Anifusionというアプリでは、5枚からLoRAを作成できる(キャラクターシートも作成してくれるので、そちらから作るのもおすすめ) - 「シーンに応じた感情表現」を細かく指示
→どういう風なプロンプトがいいかは検索をかけると出てくることもあるので、それを参照するか、またはChatGPTなどに聞くと、プロンプトを教えてくれる。
例:
long hair, red ribbon, school uniform, cheerful smile, consistent face style
こうした指定を積み重ねることで、「この子の物語をもっと読みたい」と思わせるキャラ作りが可能になります。
セリフと構成の人間らしさは「読者体験」を変える
AI漫画が伸び悩む最大の理由のひとつが「セリフの不自然さ」。
- ChatGPTなどで会話文を生成→人間が編集するのが鉄則
- 読者が感情移入できるセリフに変換するだけで印象が大きく変わる
- さらに「間(ま)」や「沈黙」をあえて取り入れるとリアルさが増す
漫画は絵だけでなく、テンポやセリフの空気感で読者体験が決まります。
SNSでの見せ方:「1話無料公開」戦略でファン化
売れる漫画は必ずと言っていいほど「SNSでの拡散」を起点にしています。
- 第1話を無料公開 → 続きが気になる読者を有料ページへ誘導
- コマ単位で切り出してX(旧Twitter)やTikTokに投稿 → 拡散率アップ
- 「縦スクロール形式」に最適化するとスマホで読みやすくバズりやすい
また、読者参加型のアンケート(次回の展開予想など)を取り入れると、ファンが物語に没入して離れにくくなる仕組みができます。
失敗しないAI漫画収益化のための注意点
AI漫画は可能性に満ちていますが、収益化を目指す上で避けるべき落とし穴も存在します。ここでは4つの重要な注意点を紹介します。
著作権問題:AI生成画像のライセンスと販売許可
AI生成画像は「誰の著作物か」という点で議論が続いています。
- Stable Diffusionなどのオープンソースは基本的に商用利用可能ですが、利用規約やモデルのライセンスは必ず確認が必要です。
※Stable Diffusionは、25年7月31日に利用規約が変更されているので、作りたい内容によっては注意が必要となります。 - Midjourneyは商用利用可
- 特に「既存キャラに似せた生成物」は二次創作問題に発展するリスクあり。
オリジナルキャラでの商用利用を基本とし、利用規約を遵守することが収益化の第一歩です。
一貫性問題:連載作品ではキャラLoRA化が必須
AI漫画最大の課題は「キャラクターが毎回違ってしまう」点です。
- 連載形式やシリーズ作品を目指す場合、LoRAでキャラを学習させることがほぼ必須。
- 顔の形や髪型、服装などを固定化することで、読者がキャラに愛着を持ちやすくなる。
- 一貫性が保たれていない漫画は「読む気が削がれる」と批判されやすい。
収益化を意識するなら、キャラの安定性にリソースを割くべきです。
収益だけを追うと読者が離れる?共感と物語性を忘れずに
AI漫画の収益化に取り組むと、つい「短期間で数を出す」ことに注力しがちです。
しかし、読者が求めているのはAIっぽい実験作品ではなく、感情移入できる物語。
- 読者がキャラに共感できるか
- ストーリーが「続きが気になる」構成になっているか
この2点を意識しないと、一時的に売れてもファンは定着しません。
稼ぐための「数」ではなく、ファンを掴む「質」を意識しましょう。
AI依存のリスク:自作力を磨くことの重要性
AIに頼り切ると、作品が「どこかで見たようなもの」になりがちです。
- プロンプトやLoRAがなければ作品を生み出せない
- 流行が変わると一気に取り残される
長期的に活動するためには、AIの力を借りつつ、自分自身の表現力やストーリー構築力を磨くことが不可欠です。
特に「キャラ設定」「世界観」「テーマ性」はAIでは生み出せない部分。ここにオリジナリティを注ぎ込むことで、AI漫画家としての強みが確立されます。
まとめ|AI漫画は「稼げる」だけじゃない。次世代の創作革命
AI漫画は単なる副業手段や「お金を稼ぐための道具」ではありません。
もっと大きな視点で見れば、人間とAIが協働して新しい表現を生み出す創作革命なのです。
副業としても、プロクリエイターとしても可能性大
AI漫画は、スキルや環境によって幅広く活用できます。
- 副業としての活用
・短編を制作してKindleやnoteで販売
・SNSで連載してPixivFANBOXで支援を得る
・月数万円レベルの安定収益を目指せる - プロクリエイターとしての活用
・企業案件(ゲーム・広告漫画・商品紹介マンガ)を受注
・出版社やメディアと協業して大規模展開
・「AIを使いこなせる漫画家」として差別化
つまり、趣味から始めても、プロとしてキャリアを築いても、AI漫画は幅広い未来を持つフィールドと言えます。
あなたの物語を、AIと一緒に世界に届けよう
AIは「作画の壁」を取り払い、誰でも物語を漫画として表現できる時代を切り開きました。
- 絵が描けなくても大丈夫
- 世界観やキャラを自分で考え、AIに補完してもらえる
- SNSや電子出版を通じて、世界中の読者に作品を届けられる
大切なのは、「自分だけの物語」を持っているかどうか。
AIはあなたの物語を増幅させ、読者へ届けるための最強の相棒となります。