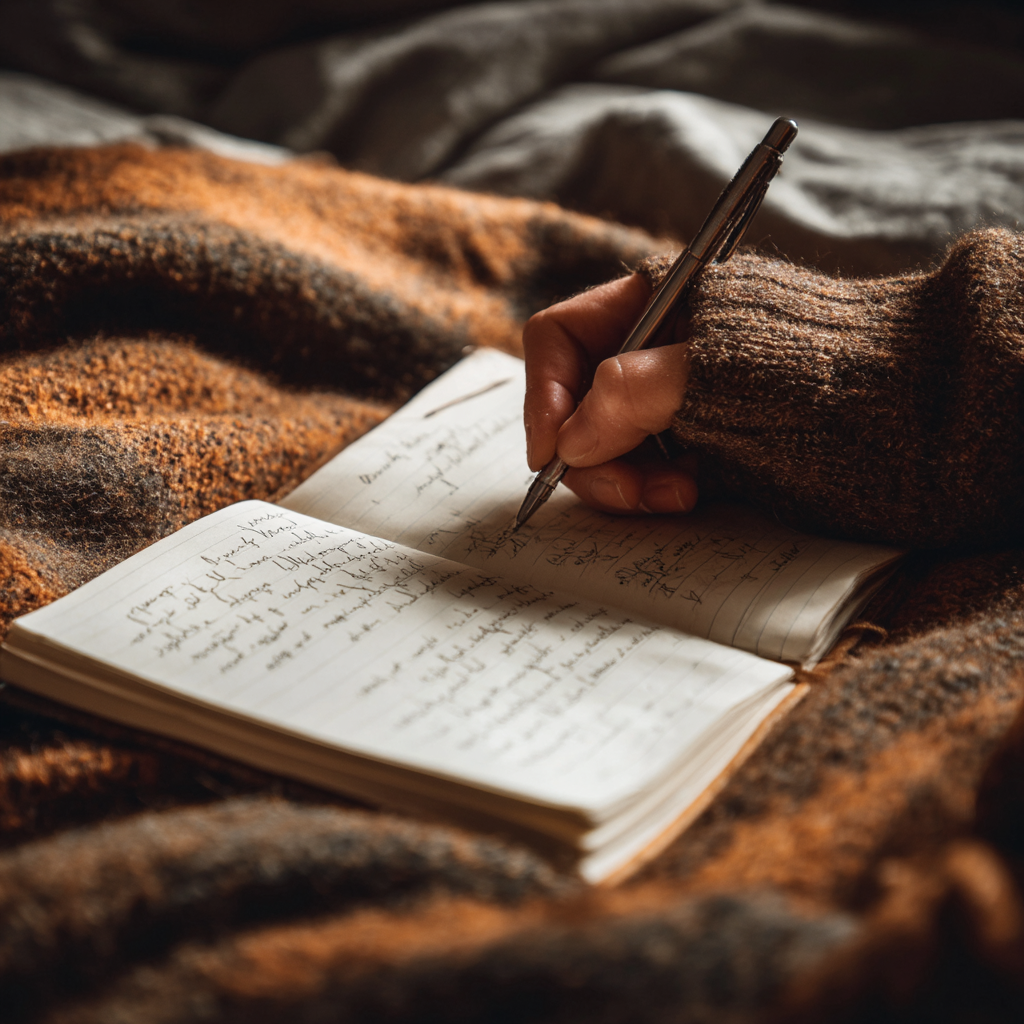AI漫画家
AI漫画を書いてみたい人が、読者に違和感を与えないために重要なのは、AIが書くイラストに違和感がないことが重要なんだ。
そこで、この記事では、AIイラストと、手書きの違いについての理解を深めてみよう!!
1. はじめに
AI技術が目覚ましい進化を遂げる中、AIによって生成されたイラストは、まるで人間の手で描かれたかのようなクオリティを誇っています。特に2023年以降、画像生成AIはスタイルの再現やディテール描写において飛躍的な進歩を見せ、作品の完成度は日を追うごとに高まっています。
その一方で、「これはAI?それとも手描き?」という問いが、クリエイターや鑑賞者の間でますます注目を集めています。本記事では、AIと手描きのイラストを見分けるポイントから、それぞれの魅力、著作権や倫理的な論点までを総合的に解説。現代の表現の在り方と、その未来を見つめ直します。
2. AIイラストと手描きイラストの見分け方
AIが進歩してきたとはいえ、いまだに、AIイラストには独特な質感や表現の傾向があり、見た人に手書きとは異なる違和感を与えることがあります。ただし、AIの特有の違和感があるからと言って、必ずしもそのイラストがAIで生成されたものとは限らないことに注意が必要です。
AIイラスト特有の違和感としては、
■ 細部の描写の不自然さ

AIは指、耳、髪の毛、アクセサリーといった細部の描写では、頻繁に違和感のあるイラストを生成します。
指の本数が多すぎたり、関節の構造があいまいだったりするので、そこで見分けがついてきます。
違和感を修正してみたのが以下の画像です。それでも手が少し変ですが…。

手書きのイラストでは、いろんな画像を参照したり、人体構造の本などを見ながら書くなどして、例えば、手がどういう構造で、どのような長さになるのかなどをきちんと理解したうえで書くことが多いため、書かれたイラストに違和感があまりないと思います。
■ 左右対称性の崩れ

AIイラストでは、目や顔のパーツが微妙にずれていたり、全体のバランスが歪んでいたりするケースも見られます。
人間の書いたイラストでは、自然な左右差が生まれますが、AIイラストでは、左右の目や顔のバランスが不自然になることがあります。
そのため、ハイライトやまつ毛、目の形に注目すると、位置や角度のずれからAIイラストだと見分けが付いてきます。
また、装飾や衣類も左右対称にデザインされている物のはずが、AIでは、形や配置が崩れることもあります。
画像では、目がかなりおかしくなっていたため、少し修正してみました。
■ 文字やマークの形状

Tシャツのロゴ、看板の文字、名札などに着目すると、意味不明な文字列や崩れた記号が描かれている場合があります。これは、AIが「文字を理解していない」ために起こる典型例です。
図では、文字がかなりぐちゃぐちゃになっているのがわかると思います。
■ 複数キャラの構図

複数の人物が絡むシーンでは、手や顔が不自然に重なったり、パーツが融合してしまうことがあります。複雑な構図ほどAIの苦手が表れやすい傾向にあります。
図では、制服が融合してしまい、左側の女の子の手がよくわからないことになっています。
本来なら以下の図のような感じになるはずなんですけどね…。
※あくまで生成AI上で修正したため、修正箇所の色味等が変わっていますが……。

■ 飲食など特定の動作

道具の使い方や動作の理解は生成AIが苦手とする傾向にあり、食事シーンを書いたイラストでは、特に顕著に見分けがつきます。
たとえば、画像のように、2本の箸でラーメンをすすろうとしたり、フォークで何かをさして食べたいのに、フォークをかじったりします。
以下はうまくいった図です。

■ キャラクターとしての整合性
AIは、人気キャラクターを再現するのは得意分野です。
しかし、生成AIはそのキャラクターの性格や細かな設定までは理解していないため、キャラクターのイメージと食い違う表情や動作をさせてしまうことがあります。
例えば、暗いキャラクターが、めちゃくちゃ明るく笑っていたり、このキャラクターはこんなことしないのにという動きの画像ができたりします。
画像は、人気キャラクターだと著作権に引っかかる可能性があるので、女の子がしなさそうな、動きをさせてみました。
■ 現実世界の風景
AIによる自動生成では、クオリティの高い風景がを書くことができます。
ただし、現実世界の風景を再現するのは苦手で、道路のスケールや、ビルの密度など、どことなく違和感を覚える画像が生成されやすくなります。
画像では、看板の文字がおかしかったり、がれきがあるのに、ビルは傷ついてなかったり、電柱と電線のスケールがおかしかったりしていますね。
■ 専門的知識が必要だったり資料が少ないもの
AIはあくまで、人が書いたものを元に学習して、イラストを生成します。そのため、ギターや着物・銃器など書くのに知識が必要でかつ書く人が少ないものは、正確に書けない傾向があります。
画像では、ギターの形がそもそもおかしくなっていますし、着物も、構造がおかしくなっています。(ライブ系の画像としては、ギターの形さえおかしくなければありかもしれませんが……)
3. AIイラストの特徴と魅力
■一貫したスタイル
AIはプロンプトを元に、統一感のあるスタイルを反復生成するのが得意です。同じテーマやキャラを、異なる構図で再現することも可能で、シリーズ制作に向いています。

■高精度なディテール
背景の描写、服の模様、光と影の質感など、非常に精緻でリアルな描写が可能。ファンタジーやSFなどのジャンルでその威力を発揮します。
■ 高速な生成
人間の制作には数時間〜数日かかる作業を、AIは数十秒〜数分でこなします。これはコンテンツ制作の効率性を大幅に引き上げるものであり、商業的な利用シーンでの優位性となっています。
4. AIと手描きの融合
AIと手描きを組み合わせることで、それぞれの長所を活かした制作が可能になります:
効率性と創造性のバランス
- AIの迅速な生成能力と人間の繊細な表現力を組み合わせることができます。
- 創作プロセスの時間短縮と質の向上の両立が可能になります
作業フローの最適化
- 構図やラフ案の生成をAIに任せ、重要なディテールは手作業で仕上げる
- 反復的・時間のかかる部分をAIに、感性が重要な部分を人間に分担させる
具体的な融合手法の例
AIラフ→手描き仕上げ
- AIで複数のラフ案や構図を素早く生成することができます
- 出来上がったラフから気に入ったものを選び、そこから手描きで細部を作り込みます
- 人間の個性や表現を加えつつ、構想段階の試行錯誤を短縮できるので時短になります
背景AI+キャラクター手描き
- 背景や環境などの複雑な要素をAIで生成します
- キャラクターや物語の中心となる要素は手描きで表現します
- キャラクターの個性を保ちながら、壮大な背景や環境を効率的に作成することができます
※画像では、別々のAIで作った背景とキャラクターを合成しています。
手描きスケッチ→AI着色/テクスチャ
- 線画やスケッチを手で描きます
- 色付けやテクスチャ生成をAIに任せます
- 人間の描線の特徴を保ちながら、複雑な彩色を効率よく着色することができます
※画像では、アニフュージョンのスケッチ機能を使って作った線画を、AIで着色してもらいました。
AI生成基本→手描き加工
- AIで基本的な絵を生成します
- 手描きで修正、加筆、強調、個性付けを行います
- AIの生成物をキャンバスのように使用し、人間ならではの要素を加えることができます
創作的な貢献と著作権面での利点
このハイブリッドアプローチには、著作権の観点からも利点があります:
- 創作的寄与の明確化
- 手描き部分が加わることで、作品への人間の創作的寄与が明確になります
- 純粋なAI生成物より著作権の主張がしやすくなる可能性があります
- 独自性の強化
- 人間の手による修正・加筆により、作品の独自性が高まります
- 同じプロンプトから生成された他のAI作品との差別化が容易になります
5. 著作権と倫理的な考慮
著作権の扱い
AIに対する著作権については、文化庁が取りまとめて発表しています。
生成・利用段階での著作権だけに絞ると、AIを利用して生成した画像をSNSなどで公表したり、販売する場合、通常の著作権侵害と同様の基準で判断されます。
AIが自動生成したイラストは、著作権保護の対象とならない可能性が高いとされています。一方で、プロンプトの工夫や加工を加えた場合、人の創作性が認められるケースもあります。
判断要素としては、
・指示・入力の分量
1. 創作的表現を具体的に示す詳細な指示は創作的寄与になり得る
AIに対して「創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示」を与えることは、創作的寄与があると評価される可能性を高めます。
例えば:
- 独自の世界観、キャラクター設定、ストーリー展開などを詳細に指示する
- 特定の構図、色使い、光の当て方、テクスチャなどの視覚的要素を具体的に指定する
- オリジナルの概念や独自の表現方法を詳細に指示する
このように、あなた自身の創作的なビジョンを具体的に表現した指示は、創作的寄与と見なされる可能性が高くなります。
2. 単なる長文の指示だけでは不十分
逆に、指示が長文・詳細であっても、それが「創作的表現に至らないアイデアを示すにとどまる」場合は、創作的寄与とは見なされません。
例えば:
- 既存の有名作品の要素を羅列しただけの長文
- 一般的な概念や広く知られている要素の単なる組み合わせ
- 詳細だが創作性のない技術的指示の集まり
分量より質が重要
この説明が強調しているのは、プロンプトの「長さ」や「分量」ではなく、その「質」や「内容」が重要だということです。短くても独創的な表現指示は創作的寄与となり得ますし、長くても独創性のない指示は創作的寄与にならない可能性があります。
実例での比較
創作的寄与が認められにくい例: 「美しい風景を描いて。山があって、川があって、木がたくさんあって、空は青くて、雲がいくつかあって、鳥も飛んでいて…」(長いが一般的な要素の羅列)
創作的寄与が認められやすい例: 「夢と現実が交差する世界。巨大な歯車が浮かぶ紫色の空の下、逆さまに生える水晶の木々。そこに佇む半透明の肌を持つ人型生物は、その目から光の粒子を放出している…」(独自の世界観や表現を具体的に指示)
・生成の試行回数
1. 試行回数自体は創作的寄与にならない
単純にAIで何度も生成を繰り返すこと自体は、創作的な寄与とは見なされません。例えば:
- 同じプロンプトで100回生成ボタンを押す
- 気に入る結果が出るまでランダムに何度も生成する
このように、単に量的に多くの試行をしただけでは、創作的な寄与があったとは認められません。いくら時間や労力をかけて何百回も生成しても、その「回数」自体に創作性は認められないということです。
2. 意図的な改良プロセスは創作的寄与になり得る
一方、以下のようなプロセスは創作的寄与として認められる可能性があります:
- 最初の生成結果を分析・評価する
- その評価に基づいてプロンプトを工夫・改良する
- 狙った表現に近づけるために試行錯誤を重ねる
- 結果を見て再度プロンプトを調整する
このように、単なる繰り返しではなく「フィードバックループを伴う意図的な改良プロセス」には創作性が認められる可能性が高まります。
実例で考える
例えば:
- 創作的寄与なし: 「美しい風景」というプロンプトだけで100回生成し、気に入った1枚を選ぶ
- 創作的寄与あり: 「山の風景」→「夕暮れの山の風景」→「オレンジ色の夕日に照らされた雪山の風景、手前に湖、遠景に松の木」というように、自分の想像する風景に近づけるためにプロンプトを発展させながら生成を繰り返す
・複数の生成物からの選択:
1. 単なる選択行為自体は創作的寄与にならない
AIが生成した複数の画像やテキストから「これが良い」と選ぶだけの行為は、著作権法上の「創作的寄与」とは見なされないという考え方です。
例えば:
- AIに「猫の絵を5枚生成して」と指示し
- 生成された5枚から気に入った1枚を選ぶだけ
この選択行為だけでは、あなたがその作品に創作的に寄与したとは言えません。単に既に作られたものから選んだだけだからです。
2. 創作的行為の一部としての選択
一方で、選択行為が「より大きな創作プロセスの一部」である場合は異なります。
例えば:
- 特定の芸術的ビジョンに基づいて複数のAI生成物を作成
- それらを比較検討しながら選択
- 選んだものをさらに編集・加工・組み合わせる
- 一連の作品シリーズとして構成する
このように、単なる「これが好き」という選択を超えて、創作的な意図や目的、専門的な判断に基づいた選択行為は、より大きな創作プロセスの一部となり得ます。
■ 二次創作・トレース問題
AIによって学習された元画像に著作権のあるものが含まれていることも多く、その使用や公開には注意が必要です。とくに、人気キャラのAI風生成や、既存作品に類似した出力を公開・商用利用する際には、ガイドラインの確認が必須です。
AIモデル(特に画像生成AI)は大量の画像データで学習されており、その中には著作権で保護されたキャラクターや作品も含まれています。このため、以下のような問題が生じます:
- 学習データに由来する著作権問題:
- AIは学習したデータの特徴を「覚えて」おり、似たようなものを生成できます
- 特に人気キャラクターや有名作品は学習データに多く含まれているため、AIが類似した出力をしやすい傾向になります。
- 意図的な模倣による問題:
- 「〇〇(有名キャラクター)のような絵を描いて」といったプロンプトで、意図的に著作物に似た出力を生成するケース
- これは単なる偶然の類似ではなく、意図的な模倣と見なされる可能性が高くなります。
具体的な注意点
- 人気キャラクターの生成について:
- 「ドラえもんのような青い猫型ロボット」などの指示は、著作権侵害のリスクが高い
- 公式のライセンスやガイドラインで許可されていない限り、商用はもちろん、ますSNSなどでの公開も問題になる可能性がある
- 既存作品に類似した出力の扱い:
- 有名なアニメスタイルや特定の作家の画風を模倣した生成物も要注意
- 「〇〇風」「〇〇っぽい」生成物でも、元の著作物の本質的な特徴を再現していれば問題になり得る
- ガイドラインの確認:
- 各版権元・権利者によって二次創作に関するスタンスは大きく異なる
- 公式に二次創作ガイドラインを公開している場合は、それに従う必要がある
- ガイドラインがない場合は、基本的に許可なく商用利用はできないと考えるべき
実務上のリスクと対策
- 商用利用の場合:
- 既存キャラクターや作品に類似したAI生成物の商用利用は、高いリスクがある
- ライセンス契約や明示的な許可なく行うべきではない
- 個人利用・非商用の場合:
- 個人的な楽しみにとどめる場合でも、公開には注意が必要
- 「私的使用」の範囲を超えてSNSなどで公開する場合、著作権問題が生じる可能性がある
- 安全な使用法:
- オリジナルのキャラクター・世界観の創作に集中する
- 特定の著作物を連想させるプロンプトを避ける
- 学習データに依存しない独自の表現を目指す
6. まとめ
AIと手描き、それぞれに違いがあり、どちらにも魅力があります。
見分けることも大切ですが、それ以上に重要なのは「何をどう表現したいか」。
スピードと精度を持つAI、人間の温度と魂を映す手描き。それぞれの良さを理解し、共存させることで、これからの創作はさらに豊かになるでしょう。